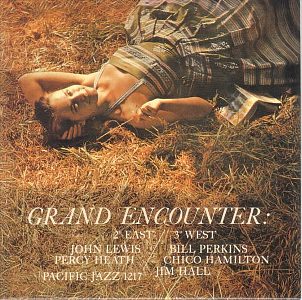JAZZの愛聴盤-10
ビートルズのキャピトル・ボックスあたりで盛り上がっているうちにもう11月も下旬、
街にはクリスマス・ツリーもお目見えだ。
できれば月に2枚は紹介していきたいと思っているこのコーナーなのだが、前回から1か月以上も間が空いてしまった。
さて冬の寒いときにはやはりジャズ・ヴォーカルがお薦め。
今回はビリー・ホリデイのJATPのライヴをご紹介します。
まずジャケットを見ていただきたい。

これぞデイヴィッド・ストーン・マーティンの最高傑作だと思っている。
この絵を初めて見たときは、ほんとうに震えた。こんなすごい絵があるのかと思った。
無駄を排した単純な線だけで成立した絵。
そこに描かれているのは、
脱ぎ捨てられた服、投げ出された送受器、ベッドに顔をうずめる裸の女……。
ただそれだけなのに、この絵はいいつくせぬほどの物語をぼくに語りかける。
この絵のモデルはマーティンの奥さんだそうだ。
けれども不世出のジャズ・シンガーと評価されながら、けっして幸福とはいえない人生を送った
ビリー・ホリデイ自身の姿とどうしても重ねてしまう。
いずれにしてもジャケ買いして損のない1枚だ。
戦後のビリーは好不調の波が激しくアルバムの出来もかなりの差があるが、このときのビリーは
すごく調子がよさそうだ。
1曲目の「ボディ・アンド・ソウル(身も心も)」のテーマからしてフェイクで入る。
こんなに軽やかなビリーの歌声を聴いていると、こっちまで幸せな気持ちになってくる。
「ビリー、よかったね」と訳もわからず声をかけたい気分になる。
彼女の代表曲である「Strange Fruit(奇妙な果実)」、彼女の体験を歌った「Travelin' Light」、
そのほかにも「He's Funny That Way」、「The Man I Love(わたしの彼氏)」、
「All of Me」など珠玉の名曲ぞろい。
バックもハワード・マギー(tp)、バック・クレイトン(tp)、ウィリー・スミス(as)、レスター・ヤング(ts)、
イリノイ・ジャケー(ts)、ウォーデル・グレイ(ts)、チャールズ・ミンガス(b)とノーマン・グランツらしい
豪華なメンバーだ。
BILLIE HOLIDAY AT JAZZ at the PHILHARMONIC
CLEF RECORDS MG C-169
2004/11/23 © ryo_parlophone
JAZZの愛聴盤-9
最近仕事の関係で外に出ることが多いのだが、ふと空を見上げて、その美しさに息を呑んでしまうことがしばしばある。
そしてその青のなかにうろこ雲やすじ雲といった秋の雲がみごとな造形と繊細な線で浮かんでいる。
思わず仕事を忘れてそのまま見上げていたくなるような10月の空である。
こういうときは夜空もほんとうに美しい。
みなさんの街はいかがですか。
こんな秋の夜にはやはり「星降るアラバマ」を聞こう。
オリジナル・タイトルは「Stars Fell on Alabama」、「アラバマに星墜ちて」ともいう。
演奏するのはキャノンボール・アダレイ・クインテットである。
ジュリアンという繊細そうな名前を持つこのアルト奏者は、その巨漢ゆえに「キャノンボール」あるいは
「ハンニバル」と呼ばれた(可哀想な話である)。
ぼくはその汗の飛び散るようなキャノンボールのアルト・サックスがそれほど好きではないのだが、
マイルズ・デイヴィスのバンドにコルトレーンとともに在籍したときのキャンノンボールは文句なくいいと思う。

このアルバムは、そのマイルズのセクステットが1959年2月にシカゴに遠征したときに、
ボスのマイルズ抜きでマーキュリー・レーベルに録音されたものである。
したがってパーソネルはキャンノンボール(as)、コルトレーン(ts)、
ウィントン・ケリー(p)、ポール・チェンバース(b)、
ジミー・コッブ(ds)ということになる。悪かろうはずがない。
演奏は「Limehouse Blues」で始まり、すでに1曲目からキャノンボールとコルトレーンの
お互いに一歩も引かないサックス・バトルが繰り広げられる。
しかしお互いに気心が知れているから、じつに余裕のあるバトルになっている。
A面B面それぞれ2曲目にはキャノンボールをフューチャーした「星降るアラバマ」と、
コルトレーンをフューチャーした「You're A Weaver of Dreams」というバラードが並んでいて、
この2曲がいずれも劣らぬ名演であるのもいい。
そして言わずもがなであるが、こういうときのウィントン・ケリーはほんとうに素晴らしい。
59年2月といえばマイルズが『カインド・オヴ・ブルー』を吹き込み、
コルトレーンが『ジャイアント・ステップス』を録音する直前である。
そういう稀有な時期にこんなリラックスしたセッションがもたれたことをとても素敵なことだとぼくは思う。
CANNONBALL ADDERLEY Quintet in chicago
MERCURY MG-20449
2004/10/16 © ryo_parlophone
JAZZの愛聴盤-8
秋の夜長にはクールなジャズを…。
『GRAND ENCOUNTER(偉大なる邂逅)』とはまた大袈裟なタイトルをつけたものである。
だれが恥ずかしいって、レコーディングに集まった当人たちがいちばん恥ずかしかっただろう。
録音は1956年2月10日、ハリウッドである。
当時はウエスト・コースト・ジャズと呼ばれる、アレンジやアンサンブルにこだわったクールなジャズの
全盛期であった(厳密にいうともうイースト・コーストでマイルズやロリンズが反撃の狼煙を上げていたけれど……)。
スタジオに集まったのはウエスト・コースト・ジャズの中心人物の一人だったドラムスのチコ・ハミルトン、
白人テナー奏者として1、2位を争う人気のビル・パーキンス、
当時はまだ西海岸で活動をしていたギタリストジム・ホールという3人に、
MJQ(モダン・ジャズ・カルテット)のピアニストジョン・ルイスとベースのパーシー・ヒース。
つまりウエスト・コーストの3人とイースト・コーストの2人が、パシフィック・ジャズという西海岸の
名門ジャズ・レーベルの録音に顔を揃えたのである。
そこで「偉大なる邂逅」(笑)。
曲はジェローム・カーンの名曲「Love Me or Leave Me」から始まる。
ジョンのやや哀愁を帯びたイントロから、テーマの提示を経て、最初に出るビル・パーキンスがやはり素晴らしい!
レスター・ヤングゆずりの柔らかくてスムーズなトーンで、美しいソロを綴ってゆく。
そのあとを受けるジム・ホールのソロがブルージーでまたいいのだ。
3番手はジョン・ルイス。MJQでおなじみの、高雅な趣きに溢れる簡潔なソロだ。
トリオで演奏される、ヴァーノン・デュークの「言い出しかねて(I Can't Get Started)」、
ジム・ホールの加わったカルテットによる、ホーギー・カーマイケルの「Skylark」、
5人による「Easy Living」、ラーナー&ロウの「恋をしたみたい(Almost Like Being Love)」と、
スタンダード・ナンバーがずらりと並ぶ。
そんななかで、1曲だけジョン・ルイスによるブルーズ「2度東、3度西(2 Degrees East-3 Degrees West)」が
また素晴らしい。タイトルはもちろん5人の出会いをかけたもの。
チコのトレードマークのようなティンパニのバックに乗って、テナーとピアノがユニゾンでテーマを奏で、
そのままそれをバッキングにベースのソロが始まる。かっこいい!!
ジム・ホールの渋いギター・ソロを挟んで、ビルのテナーがスタイリッシュに空間を埋めてゆく、
そのバックのジョンの音数を抑えた簡素なバッキングも見事だ。
もうひとつジャケットがまた素晴らしい。
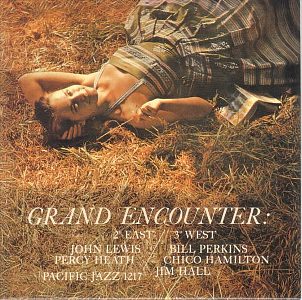
ぼくは最近のヴィーナス・レコードのように、露骨に女性のヌードや下着姿をあしらったジャケットが
好きではないが、こういう健康的なものには弱い。
中身を知らなくても思わずジャケ買いしてしまいそうな1枚です。
"GRAND ENCOUNTER : 2°EAST / 3°WEST"
PACIFFIC JAZZ PJ-1217
2004/09/16 © ryo_parlophone
JAZZの愛聴盤-7
夏の熱い夜にはホットなホットなジャズを(笑)。
ホーギー・カーマイケルの「スター・ダスト」はスタンダード・ナンバーとして
多くのジャズ・プレイヤーに取り上げられてきたが、数ある名演の中でも一番忘れがたいのが、
この1947年8月4日の「ジャスト・ジャズ・コンサート」における
ライオネル・ハンプトン・オール・スターズの演奏だろう。

とにかく最初から最後まで聴衆を捉えて離さない演奏の連続で、聴衆はいたるところで歓声を上げどよめいている。
ライオネル・ハンプトン(vib)のシンプルで美しいイントロに続いて、
まずウィリー・スミス(as)がソロを取るが、その出だしのフレーズの情緒連綿たるトーンでもう客席はどっと沸きあがる。
ダチョウ倶楽部ではないが「つかみはオッケー」である。
ウィリー・スミスはスイング時代にジョニー・ホッジス、ベニー・カーターと並んで3大アルトと呼ばれた名手であるが、
ややオーヴァーともいえるアクセントで聴衆を釘づけにしてしまう。
つづいてトランペットのチャーリー・シェイヴァース。
まず出だしのフレーズが素晴らしい。
低音を主調とした落ち着いたトーンながら、ときどきユーモラスな効果音的な音をはさみながらのソロで、聴衆は大喜び。
3番手はテナー・サックスのコーキー・コーコランである。
コールマン・ホーキンズの流れを汲む名手だが、ヴィブラートの効いた軽やかで伸びのあるトーンで、
速いパッセージとゆったりとしたフレーズの対比も巧みだ。
次のソロはベーシストのスラム・スチュアート。
弓弾きしながらその1オクターブ上をハミングするという独特のスタイルで40年代には大変人気のあった人だ。
ここでもハミングのなかにこっそり「マネー、マネー」ということばを織り交ぜて聴衆を喜ばせたり、
サーヴィスたっぷりのソロである。
つづいてピアノのトミー・トッドとギターのバーニー・ケッセルが半コーラスずつソロを分ける。
ケッセルはジャズ・ギタリストとして1、2を争う名手だが、このころはまだ新人だった。
彼のソロだけがバップ・イデオムに基づいているのも微笑ましい。
そして最後に真打、ライオネル・ハンプトンの登場である。
とにかくこのソロが半端ではない。15分の演奏時間のうちなんと6分に及ぶソロであるが、あとからあとから、
次から次へと素晴らしいフレーズが出てくる。汲めども尽きせぬ泉のごとくとはこのことだ。
スイングするとはどういうことか、そのお手本のようなソロである。
モダン・ジャズの世界ではヴィブラフォンというとミルト・ジャクソンが第一人者だが、
ミルトの前にハンプトンという巨匠がいたから、ヴィブラフォンがジャズの世界でソロ楽器たり得たということを、
あらためて思い知らされるような名演である。
勢い込んで叩く最初のフレーズから、ダブル・テンポになって次第に熱を帯びてゆき、最後はブルースで締めくくるのだが、
何度聞いても鳥肌の立つようなソロである。
まだ聞いたことのない方はぜひ一度聞いてみてほしい。
このCDにはあと3曲収められているが、それは聞かなくてもいい(笑)。
なぜならライオネル・ハンプトンがいないのである。
ジャケットにはデカデカと「STAR DUST BY LIONEL HAMPTON ALL STARS」と書いてあるが、
よく見るとほかの3曲は「BY THE ALL STARS」としか書いてない。たしかに……(笑)。
しかしこの1曲目のために買ってよい1枚である。
それにしてもボス、コンサートの最中に演奏しないで何してたんだろう?(笑)。
LIONEL HAMPTON ALL STARS "STAR DUST"
DECCA DL9055
2004/08/25 © ryo_parlophone
JAZZの愛聴盤-6

ロイ・ヘインズのリーダー・アルバムは『ウィー・スリー』にしても、
この『アウト・オヴ・ジ・アフタヌーン』にしても共演者が魅力的で人気が高い。
ではロイ・ヘインズはドラマーとしてはどうなのか、と問われればぼくは一流のドラマーだと答えたい。
たしかに先行するアート・ブレイキーやマックス・ローチ、後輩のエルヴィン・ジョーンズやトニー・ウイリアムズのように、
時代を切り拓いたミュージシャンというのではないのかもしれない。
しかし麻薬療養中のエルヴィンに代わってコルトレーン・カルテットで代役として叩いた
1963年のニューポート・ジャズ・フェスティヴァルの「My Favorite Things」を聞けば、
ロイ・ヘインズもずば抜けた才能の持ち主であることは論を俟たないだろう。
このアルバムでもソロは控えめながら、極めて多彩でカラフルなドラミングを聞かせてくれる。
ただ(矛盾したことを言うようかも知れないが)、このアルバムの主人公はやはり、ローランド・カークである。
(盲目であるため)サングラスをかけ、一度に二つや三つの楽器を口にくわえて吹き鳴らすさまから、
「グロテスク・ジャズ」なる不本意な呼ばれ方をされた時期もあったようだが、
カークの音楽性はきわめて正統的な、ジャズの豊かさ・楽しさを感じさせるものだ。
ここではオリジナル3曲、スタンダード4曲という構成だが、スタンダードのできがいずれ劣らず素晴らしい。
とくにお勧めは冒頭の「Moon Ray」とB面の「If I Should Loose You」だ。
テナー・サックス、マンゼロ、ストリッチ、フルートというような楽器を交互に、ときには同時に吹きながら、
ブルースを基本としながらコルトレーン・イデオムを消化したスインギーな演奏を聞かせてくれる。
共演者では、ピアノのトミー・フラナガンが燻し銀のようなソロを聞かせてくれて素晴らしい。
ROY HAYNES QUARTET "OUT OF THE AFTERNOON"
impulse! STEREO A-23
2004/07/28 © ryo_parlophone

|