JAZZの愛聴盤-28チャールズ・ロイド 『フォレスト・フラワー』 このアルバムが録音された1966年前後のことをちょっと振り返ってみよう。 まずマイルズ・デイヴィスのコンボは1964年秋にウエイン・ショーターが加入したことによって鉄壁の布陣となり、65年には『E.S.P.』、66年には『マイルズ・スマイルズ』を吹き込んでいる。 コルトレーンは65年に『至上の愛』をリリースして神の世界に近づき、同年6月にはもっともフリーに傾斜した問題作『アセンション』を録音している。 66年はブルーノートがオーネット・コールマン(as)やセシル・テイラー(p)、ドン・チェリー(tp)らと契約し、彼らの新録音が続々とリリースされた年でもあった。 ポップスの世界ではビートルズが66年に『リヴォルヴァー』をリリースし、そのサイケデリックな音世界は翌年の『サージェント・ペパーズ』に受け継がれていくが、それをいち早くカヴァーしたジミ・ヘンドリクスによってロック・ギターの世界が大きく変わろうとしていたのもこのころだ。 チャールズ・ロイド(ts)がキース・ジャレット(p)、セシル・マクビー(b)、ジャック・ディジョネット(ds)という、今から見れば目も眩むようなリズム・セクションを率いてモンタレー・ジャズ・フェスティヴァルに登場したのは1966年9月のことで、聴衆から熱狂的に受け入れられるようすがこのアルバムにはとらえられている。  アルバムの中心はもちろん「Forest Flower-Sunrise」、「Forest Flower-Sunset」という組曲だ。 ロイドがフルートに持ち替える「Sorcery」はエイト・ビートのジャレットらしいオリジナル、マクビーが書いたバラード「Song of Her」はロイド版「ナイーマ」(コルトレーンのオリジナルで従来の表記は「ネイマ」)といった趣きで、ジャレットの美しいソロも必聴だ。 CHARLES LLOYD "FOREST FLOWER"
ATLANTIC SD 1473
2007/01/18 © ryo_parlophone 追悼:愛するアニタasahi.com から記事を引用する。 米ジャズ歌手、アニタ・オデイさん アニタ・オデイさん(米ジャズ歌手)が23日、ロサンゼルスの病院で死去、87歳。 8月の「JAZZの愛聴盤」で『真夏の夜のジャズ』を取り上げたときにアニタのことにもちょっと触れた。  アルバムは「'S Wonderful」で始まる。 『真夏の〜』で聴衆を釘付けにした「Sweet Georgia Brown」のようなアドリブの応酬が楽しめるのは、急速調で展開される「Them There Eyes」だ。 バックはOscar Peterson(p)、Herb Ellis(g)、Ray Brown(b)、John Poole(ds)という名手たち。 レイのベースはもちろんだが、「I've Got The World On A String」など、ハーブ・エリスのギターもいぶし銀のような美しさだ。 スタン・ケントンの歌姫としてジューン・クリスティ、クリス・コナーへとつづくハスキー・ヴォイスの流れをつくったアニタ。 ANITA O'DAY "ANITA SINGS THE MOST"
CLEF MG V-8259
2006/11/26 © ryo_parlophone JAZZの愛聴盤-27ソニー・スティット 『チューンナップ!』 ソニー・スティットのレコードというと、1949年のビ・バップ期の名盤『スティット・パウエル・JJ』 (プレスティッジ)を初めとして、ルーストの名演『ペン・オヴ・クインシー』、 ヴァーヴに残した『シッツ・イン・ウィズ・オスカー・ピータースン』や『モダン・ジャズ・ジャイアンツ』など、 優れた演奏をいくつも思い浮かべることができる。 そんななかでぼくがときどき聴きたくなるのが、70年代に入ってなお存在感を示したコブルストーンの 『チューンナップ!』だ。  スティットといえばアルトの名手ながら、あまりにチャーリー・パーカーに似ているので、
かれの存命中はもっぱらテナーを吹いていたことで有名だ。 ここではバリー・ハリス(p)、サム・ジョーンズ(b)、アラン・ドウソン(ds)という実力のしっかりしたトリオに サポートされて、タイトル曲(マイルズ・デイヴィス作)や自作のブルーズ、「Groovin' High」 (ディzジー・ガレスピー作)といったバップ期のオリジナルと、「言い出しかねて」、「I Got Rhythm」といった スタンダードが絶妙に並べられ、ゆったりとした時間のなかでスインギーなジャズの醍醐味を味わうことができる。 例によって硬質だがスインギーなバリー、伸びやかなサム、地味だけれど堅実にサポートするアランのトリオもじつに味わい深い。 音源がミューズ・レーベルに移ってからはレコードでもCDでも国内盤が出ていたし、数年前には紙ジャケもリリースされたが、
しばらくまえに廃盤になっているようだ。 SONNY STITT:Tune-Up!
COBBLESTONE 9013
special thanks to Mr.M54 追悼:デューク・ジョーダンasahi.com から記事を引用する。 米ジャズピアニスト、デューク・ジョーダンさん デューク・ジョーダンさん(ジャズピアニスト)が、ニューヨーク・タイムズのインターネット版などによると、 8日死去、84歳。チャーリー・パーカー・グループで演奏し、50年代にニューヨークを中心に活躍。70年代には チェット・ベイカーらと共演。「フライト・トゥ・デンマーク」などの作品を残した。親日家としても知られ、 たびたび来日し、各地で演奏会を開いた。 デューク・ジョーダンの名前を初めて覚えたのはご多分に漏れずチャーリー・パーカーのアルバムからだった。 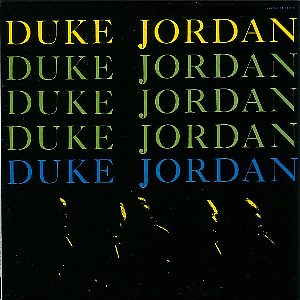 さて、今晩はシグナル・レーベルに遺されたリーダー・アルバム、『トリオ・アンド・クインテット』を聴こう。 ぼくのお気に入りはやはりトリオのほうだが、冒頭の自作曲「Forecast」の軽快な愛らしさ、2曲め、
これもオリジナルの「Sultry Eye」の美しいバラード、そしてとくに素晴らしいのが3曲めの
「私からは奪えない They Can't Take That Away from Me」だ。 まったくジャズでは食えない時期も長く、一時はタクシーの運転手をしていたこともあるというジョーダンだが、
1973年にデンマークのレーベルSteeple Chaseに「再発見」されて『FLIGHT TO DENMARK』で復活してからの活躍は
ジャズ・ファンの方ならご存知だろう。 とにかくソロのアドリブがそのままひとつの曲になってしまいそうなメロディアスな美しさはジョーダンの特質だ。 追記 ブルー・ノートの名盤『FLIGHT TO JORDAN』は邦題『フライト・トゥ・ジョーダン』でまちがいではないのだが、
ここはやはり『フライト・トゥ・ヨルダン』としたいところ。 DUKE JORDAN / TRIO AND QUINTET
signal
2006/08/16 © ryo_parlophone JAZZの愛聴盤-26カール・パーキンス(p、「ブルー・スエード・シューズ」で有名なロカビリーの名歌手とは別人)の名前を
最初に聞いたのはどこでだっただろう。 パーキンスのピアノには強烈なスイング感があり、その圧倒的な迫力は一度聴いたら忘れられないほどだが、
その奏法はたいへんに独特のものだ。  とくに自作のブルーズ曲3曲はどれもブルーでソウルフルな魅力に溢れていて、心を捉えて離さない。 ベースはウエスト・コーストの第1人者ルロイ・ヴィネガー、ドラムはローレンス・マーブルという布陣で、 これで録音がよければ申し分ないところなのだが、どこかで高音質のリマスタリングを施した紙ジャケで 出してもらえないだろうか。 introducing... CARL PERKINS
DOOTOON LP 211
2006/07/05 © ryo_parlophone

| |||||||