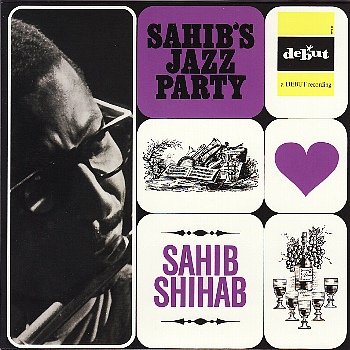SAHIB'S JAZZ PARTY
サヒブ・シハブという、いっぷう変わった名のジャズマンの演奏を初めて耳にしたのはどのレコードだったか。
おそらくセロニアス・モンクの初期のセッションを集めた2枚のブルーノート盤だったのだろう。
それからしばらくして、今度はプレスティッジのコルトレーンのレコードで、バリトンを吹いているサヒブ・シハブを聴いた。
けれどもそこでのかれのプレイはそんなに印象に残るものではなかった。
今回ご紹介する『サヒブズ・ジャズ・パーティー』は1963年にコペンハーゲンのカフェ・モンマルトルで収録されたライヴで、アラン・ボチンスキー(flh)、オレ・モリン(g)、ニールス・ペデルセン(b)、アレックス・リール(ds)といったミュージシャンを従えて、アルト、ソプラノ、バリトン、それにフルートという管楽器を自由に操るかれの熱演を聴くことができる。
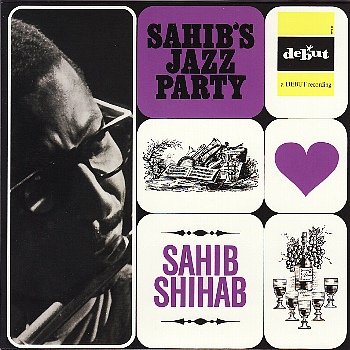
このアルバムを知ったきっかけは、紙ジャケ探検隊の掲示板のyasu さんという方の書き込みだった。
そのときはただちょっと興味をもっただけだったのだけれど、このまえ行きつけのタワレコを覗いてみると、なんとこの紙ジャケだけが、ジャケットを正面に3、4枚ディスプレイされていたのだ。
そんなにジャズ人口が多いとも思えない田舎のタワレコで、紙ジャケが正面を向けて紹介されているのは、ぼくの記憶ではマーティ・ペイチの"踊り子とお風呂"以来のことだ。
これはひょっとしたらクラブ・ジャズ周辺で盛り上がってるのかな、と思って買ってみた。
まずM-1「4070 Blues」で、いきなり飛び出すニールス・ヘニング・オルステッド・ペデルセンのウォーキング・ベースにぶっ飛ぶ!
解説を読むと、まだこのとき17歳だそうだ。
ペデルセンのことは以前どこかにも書いたけれど、とにかくその驚異的なテクニックはスコット・ラファロの再来といってもおかしくないほどだった。
若くして亡くなったのは残念だが、17歳のときの録音が残っていたなんて…!
バッキングにソロに、縦横無尽に駆け巡るすばらしいベースを聴かせてくれる。
サヒブのフルートは声も絡ませながらダーティな音色でひたすらハードに吹きまくるもので、個人的には好みではないが、熱いジャズがお好みの人にはいいかもしれない。
オレ・モリンのギターあまりテクニカルではなく、太い音でバリバリと弾くタイプでバンドとしての疾走感を感じさせる演奏だ。
ぼくが気に入ったのはアナログ盤でいうとB 面に当たる「Conversations part I〜III」という組曲風の作品。
ここでのサヒブはバリトン、ソプラノ、フルートを駆使して豊かな音楽性を感じさせる。
とくにバリトンは50年代のコルトレーンのアルバムで聞かれたような、無骨であまり面白味のないソロではなくなっていて、渡欧後の進歩を感じさせる。
パートII における抒情的なフルートのソロもいい。
フリューゲルホルンのボチンスキーもけっしてテクニシャンではないが、クールにアドリブを組み立てるタイプのようで、それぞれの楽曲の曲想を生かしたうまいアシストを聴かせてくれる。
アレックス・リールも繊細さと豪快さを兼ね備えたドラミングで、熱いプレイを煽り立てる。
音のほうは鮮度がすばらしくとても46年も前の録音とは思えない!
とくにペデルセンのベースはよく録れている。
ぼくはいままで何枚かHQCD を聴いているが、これがHQCD の実力としたら大したものだ。
最近モダン・ジャズを聴いてないなあ〜…久しぶりに熱い演奏に身を委ねてみたい…と思ってる人には最適のアルバムです。
"SAHIB'S JAZZ PARTY" SAHIB SHIHAB
debut 688 604 ZL
2009/04/14 © ryo_parlophone
雨のヴィレッジ・ヴァンガード
梅雨というよりまるで集中豪雨のようだった先週の金曜日の夜、仕事仲間の飲み会があった。
いつもなら電車で行くのだが、妻が送ってくれるという。
あまりにすごい雨なので厚意に甘えることにした。
妻のクルマは最近CD チェンジャーの調子があまりよくないみたいで、MD をかけることが多いのだが、そのときは珍しくFM がついていた。
しばらくすると助手席に座った娘がバレエの練習の疲れのせいかうとうとし始める。
FM のにぎやかなおしゃべりを避けて妻は1枚のMD を挿入した。
流れてきたのはビル・エヴァンスの「Waltz for Debby」だった。
ぼくは思わずこころのなかで「ほう」とつぶやいてしまった。
陰鬱に垂れ込めた雲と、絶え間なく降り注ぐ雨。
鈍色の空にエヴァンスの愛らしいワルツのテーマが素敵に似合った。

それからがおもしろかった。
ぼくが座っているのは助手席側の娘の後ろの座席だ。
エヴァンスのピアノは右のスピーカーからやや遠めに聞こえ、スコット・ラファロのベースがすぐ左のスピーカーから沸きあがってくる。
それは大げさにいえば「かつてないスリリングな体験」だった(笑。
もちろんポール・モティアンのドラムスも対等なインプロヴィゼイションを仕掛けてくるのだが、エヴァンスとラファロのデュオは、まるでヴァイオリン・ソナタにおけるピアノとヴァイオリンのように、ときには恋人のように、ときにはライヴァルのように、寄り添ったり競い合ったりして音楽を美しく前進させてゆく。
いつもはピアノの側から聴くインプロヴィゼイションをベースの側から聴くと、端正な緊張感が存在しているのに気づかされるのだった。
そんな体験がおもしろかったぼくは、日曜日の夜、左チャンネルのスピーカーの前でビル・エヴァンスのCD を聴いたのだった。
考えてみると、昔ジャズ喫茶に通っていたころには、バランスのいい中央の席に座れることは稀で、片方のスピーカーに近い座席に座ることがふつうだった。
パラゴンの左チャンネルの真ん前に座ったこともあったなあ(笑。
こうやって聴いてると忘れかけていた学生時代のことが甦ってくる…。
などと感慨に耽っていたところにいきなり来た!
ぼくはいつのまにかヴィレッジ・ヴァンガードの客席に座っているような錯覚に襲われたのである。
小さなクラブのような場所でライヴが行われるとき、ぼくらは必然的にミュージシャンの間近に陣取ることになる。
アート・ペッパー(as)カルテットのときも、ミルト・ジャクソン(vib)〜レイ・ブラウン(b)クインテットのときもそうだった。
目の前にベーシストがいたり、ドラマーがいたりしたのだ。
2本のスピーカーを結ぶ線を底辺とする三角形の頂点に座るだけがオーディオの楽しみかたではない。
たまには片方のチャンネルの前に座ってみる。
それがとくにライヴのCD だったりすると新しい楽しみかたになる。
そんなことを実感した夜だった。
"Waltz for Debby" Bill Evans Trio
RIVERSIDE 9399
2007/07/12 © ryo_parlophone

|